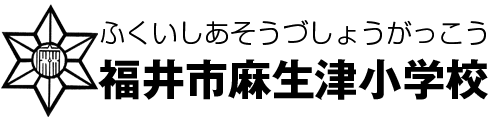学校教育目標
自ら学び、未来を拓く児童の育成
めざす学校像
自らの力を発揮し、生きる力をつなぐ学校
新しい学力観を強く意識し、基礎基本の定着にとどまらず、資質・能力の基盤を生きる力として「つなぐ」視野と意識の転換を図っています。子どもも教職員も「自らの力を出す」ことができるように、皆で力を合わせていきます。子どもの姿に表れる資質・能力の三つの柱の基盤を大事にしながら、園小中の接続を意識し、生きる力としてつないでいきます。
知識・技能:感じること、気づくこと
思考力・判断力・表現力:見通し見直し工夫しやり直すこと、思いを自分の言葉や表現で出すこと
学びに向かう力:好奇心・粘り強さ、友達等による支えを自分なりに取り込むこと

令和3・4年度の園小接続の取組にて、系統性・継続性を意識した本校の接続の重点をまとめました。子どもたちが意欲と意志を膨らませ、出会い、気づき、もっと好きになる今日1日になるよう、異校種間の連携・接続を続けています。不登校予防等、様々な課題を解決するために、生徒指導・教育相談・特別支援の枠を超え、子どもを支えようとしています。
麻生津小学校区 接続の重点 ←クリックすると資料をご覧いただけます
めざす麻生津っ子
年度ごとに重点テーマを設定し、教育をより豊かなものにしようとしています。特に、認知能力と非認知能力が絡むように伸びていくことに着目し、子どもの内側で培われる「学びに向かう力」を大切にしています。
令和3年度:「子どもの学ぼうとする姿」を捉え「~しようとする」志向性を重視
令和4年度:志向性と 資質・能力の核「情意」(意欲と意志)を重視
令和5年度:「情意」と「躍動」~意欲と意志をわき上がらせ、いきいきと動く子どもの姿に着目
令和6年度:三つのしこう「志向・試行・思考」を繰り上げる
令和7年度:三つのしこう「志向・試行・思考」を繰り上げる
【知・徳・体と資質・能力のつながり】
認知能力と非認知能力が絡み合って、情意(意欲と意志)を核に伸びることに着目して取り組みを進めています。
知(学ぶ意欲、思考力・表現力):進んで学び、考える力・表現する力を高めようとする子
徳(他者との協働):自分の力を出し、認め合い、協力して行動しようとする子
体(心身の健康としなやかさ):心と体を大切にし、粘り強くやってみようとする子

スクールプラン
あそうづっ子が資質・能力「生きる力のもと」を膨らませ、未来を拓く力を育むことができるよう、スクールプランを改定し、重点目標を設定、具体的な取組と数値目標を明記しています。インクルーシブ教育も含め、全ての子どもが力を発揮できる居場所となれるよう、家庭・地域とともに課題に取り組み、一つずつ学校運営の改善につなげていきます。皆様のご理解・ご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

研究主題
研究主題 :自ら学び、未来を拓く
令和7年度テーマ:しこう「志向・試行・思考」を繰り上げる授業づくり

本校は、平成17年度から、「確かな学力 いきいき麻生津っ子を目指して」という研究主題のもとに授業研究を進めてきました。令和3年度からは、これからの子どもたちの育成に必要な新しい学力観に向き合うために、学校教育目標「自ら学び、未来を拓く児童の育成」を掲げ、ICTの活用も進めながら、子どもの姿に着目した授業改善を核として研究を進めています。
時代が求める資質・能力に合わせ、授業や評価のあり方にも変革が必要です。教員自身が、教育が担う変化を自覚し、学び続けることの大切さを強く意識することが必要な時代となっています。

コロナ禍における急激な社会情勢の変化や生活様式の変化に伴い、その実態に即する「今」と子どもたちの生きる時代を見通した「将来」の両方を見据えることが重要になってきました。教員の働き方改革・業務改善の背景も踏まえ、持続可能な「学び続ける機会」として、教員自身が決めた日時・教科の一授業を外に開き、なかまの教員や地域の園・中学校と学び合う「一人一授業」研究を継続しています。生きる力を支える「もと」となる様々な力を、教育の基盤として意識し、教員が授業改善を図ることで、自分の力を主体的に発揮しようとする子どもたちを育てようとしています。
生徒指導・教育相談・特別支援
本校では、様々な役割を担う教職員同士がチームとして連携できるよう、生徒指導・教育相談・特別支援の枠を超えて、必要な環境、空間や時間、関わりなどを工夫し、子ども一人ひとりを支えようとしています。